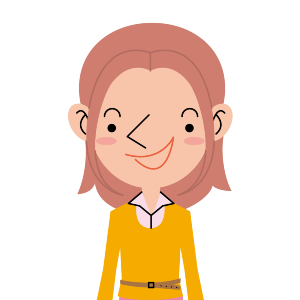
YAKOさんて、色んな仕事をしてますけど、どんな風に仕事を取ってきたり、調整してるんですか?
こういう質問は良く聞かれます。あと、「パラレルワーカーです」というと「副業とどう違うんですか?」とも良く聞かれます。

この記事では、WEBクリエイター歴15年、エディトリアルデザイナーとしては23年の実績を持つ私の仕事のスタイルをご紹介します。
副業とパラレルワーカーの違い
副業とパラレルワーカーの定義は色々あると思いますが、ここでは私の感覚で違いを書いてみようと思います。
副業とは
副業は、正社員として主であるメインの仕事があり、プラスαの収入を得るために行うもの。主であるメインの仕事と似たようなジャンルのものだと、情報流出の恐れから会社の規約に反することもあるので、一般的には収入増のためだけに副業をする人が多いんじゃないでしょうか。
会社が終わってから、バーで仕事するとか。
週末だけアルバイトするとか。
WEB制作を受注するのも、副業といえます。
副業とは、あくまでも主である本業があり、サブとしての仕事を副業と呼んでます。副業は自分の専門分野に限らず、コンビニのバイトや週末の引越し業とかのアルバイトなど、収入増を目的にしたもの、というイメージ。
パラレルワーカーとは
メインがひとつ、というわけではなく、2つ、3つと色んな仕事を同じ熱量で仕事をする働き方です。
アルバイトを複数掛け持ちしていても、パラレルワーカーとは呼びません。
自分のスキルで仕事を取り、どこかの企業に属さずに複数の仕事をする働き方が「パラレルワーカー」。開業届けを出して、ビジネスとして成立しているかどうか、というイメージ。
パラレルワーカーとしての働き方
私の場合、企業の広報としてのプロモーション活動、WEB制作やマーケティング、アナリティクス解析等を行うコンサル業を軸に、個人事業主向けのWEB制作・コンサル、パンフレットや看板デザイン制作、このサイトのような自己完結型のWEBコンテンツ制作などを行っています。
私がパラレルワーカーとして仕事をしている、ということを理解しているクライアントからの仕事だけを受けるようにしています。というのは、複数仕事を回しているので「自分のところだけに集中して欲しい」と考えているクライアントとは仕事をしません。
専属として働くならそれだけの報酬をいただくというスタンスでいますが、パラレルで働いた方がひとつに縛られて働くよりも自由で収入もいいので。
なので、必然的に私の都合に合わせて依頼してくれるクライアントがほとんどです。
1日24時間を自由に配分する
あるクライアントの例でいうと、最初こそ打ち合わせはクライアントの事務所まで赴きますが、パラレルワーカーとして働いていて時間的な制限があるということを理解してくださっているクライアントばかりなので、お互いに都合の合う日、時間を決め、カフェで待ち合わせて打ち合わせをしています。
「YAKOさんの都合のいい時間はいつですか?」と聞いてくださることがほとんどで、「朝6:30~8:30まで、Wifiの繋がる○○カフェで」というようなことも提案することもして実際に朝食を食べながらの打ち合わせなどもやっています。
これはクライアントと制作者の間で上下関係ができてしまっていると叶わないスタイルです。
中には「ブラッククライアント」としか言い様がない、プロの意見を聞かないクライアントも稀にいますが、そういう場合は一回こっきりの仕事にし、二回目からは受けないようにしています。
パラレルワーカーは、収入源が複数あるので精神的に余裕があり、クライアントを選べるというメリットがあります。
また、私の場合、すべてクチコミと紹介だけの受注なので、ありがたいことにクライアントの方から「作って欲しい」というお気持ちでいてくれるので、ある程度自由な働き方ができているのかな、と思います。
いつでも、どこでも仕事をする
こういうことを書くと「ワーカーホリックじゃないか!」と思われるかもしれませんね。
でも、「働かされている」のと「自主的に好んで働いている」というのは精神的にも大きな違いがあります。
私の場合、PCとWifi環境さえあればどこでも仕事ができるので、海外に出るときも必ずPCは持っていきます。
ベトナム滞在中に、クライアントのWEBサイトがGoogleの圏外飛ばしに遭い、Facebookのメッセンジャーを通して悲愴な相談にも柔軟に対応できました。
いつでも、どこでも仕事ができるというのは、チャンスを逃しませんし、既存のクライアントへのフォローを徹底できます。自分の働く時間や場所を自由に自分で決められる、というメリットがあるのです。
できる! やりたい! と思った仕事は自分で広げる
たとえば、クライアントから「写真もクオリティの高いのが欲しいんだけど…だれかフォトグラファー知らない?」なんてことも聞かれることがあります。
そんなとき、一眼レフを持っていて知識を身につけておけば「私、写真やってます。できますよ」と提案することができます。写真は視覚的に力量を伝えやすいし、自分のポートフォリオサイトに載せておいてURLを教えて差し上げあればいいのです。
WEB制作も含めてトータルで受注できればフォトグラファーに頼むよりも安いし、楽だし、クライアントも喜んでいただけます。
そんな風に、自分で仕事を広げていくこともパラレルワーカーに必要なスキルだといえます。
パラレルワーカーをめざす人へ
パラレルワーカーという働き方は、なにも特別なものではありません。
でも、パラレルワークに向いている職業というのは確実にあります。
私がやっているクリエイターという仕事は、非常にパラレルワークに向いていると思います。その他でしたら、たとえばカイロプラクターがヨガやピラティスの資格を取って、施術とスタジオの両方で働くとか、講演会やセミナーを主催するなどのパラレルワークも可能ですね。
でもやはり、WEB関連の職業は、クライアントが目の前にいなくてもFaceTime等でいつでも打ち合わせもできますし、海外からのリモートワークも可能ですから、やはり一番パラレルワークに適していると思います。
これからパラレルワーカーというスタイルを目指したい人は、WEBデザイナーやWEBエンジニアになるための勉強をすれば叶えられます。
「え〜、そんなの大変! 無理ですよ〜」という声が聞こえてきそうですが、全然大丈夫です。あなたにもできます。
しかも、司法試験や医師国家試験に受からないとなれないものでもなく、半年もしっかりスクールで学べば年内にはWEBデザイナー、エンジニアとして新しい道が開けます。
「でも、私もう30歳(40歳)過ぎなんだけど…」と不安に思っている方もいるかもしれませんが、そういう人は今の会社員としての仕事を維持しながら、アフターワークでスクールに通い、副業として仕事をすればいいのです。
生活費や学費は会社員としての給料から捻出できて、リスクゼロ。
副業として少しずつ実績を積んでいけば、いずれ「副」ではなくなる時がやってきます。
そして転職をゴールにする必要もなく、自分でWEBアプリケーションを作って公開すればマネタイズも可能。アイデア次第でなんでもできるのが、WEBの仕事の醍醐味であり魅力です。
自分の可能性や選択肢は多ければ多いほどいい
精神的に追い詰められてうつになってしまうのは、「逃げ道がない」状況にいるからです。
もし、会社でパワハラや同僚からのイジメに遭っても、あなたに他に選択肢があれば心の拠り所になるはずです。会社を辞めて転職しよう、という気にもなるでしょう。「この会社を辞めたら後がない」と思うから、逃げ道がなくなるのです。
「私にできるのはこれくらい」「私はこれくらいしかできない」と自分に制限をかける必要もありません。
あなた自身が自分の中に秘める才能や能力に気がついていない可能性もあるし、収入が増えればそれだけ自由も手に入れられます。
可能性を増やすには、
- 世の中にアンテナを張ること
- 常に学ぶ姿勢を忘れないこと
- 好奇心を持って、色んなことに取り組むこと
- インターネットや他人の「マイナス意見」に足を引っ張られないこと
です。
自分の夢や目標を語って、応援してくれたりサポートしてくれる友達や親ならいいですが、とくに詳しくもないのにあれこれと理由をつけて反対してきたり、「あなたにはできっこない」という意見は一切聞かなくていいです。
あなたの人生は、あなたのもの。あなたの人生に責任を負えるのは、あなただけなのですから。
どうぞ、あなた自身を開放して、色々なことに勇気を持ってチャレンジしてみてください。
WEBクリエイターになりたい人へ
WEBクリエイターやWEBエンジニアになりたい人は、当サイトで優良なスクールを紹介しているのでご参考にしてみてください。
どのスクールがあなたに合っているのかわからない、ということであれば、お問い合わせからご連絡いただければWEBクリエイターとしての経験から判断し、あなたにおすすめのスクールをご提案します。

